|
1:グァテマラってどんなところ?
2:コナビグアってなに?
|
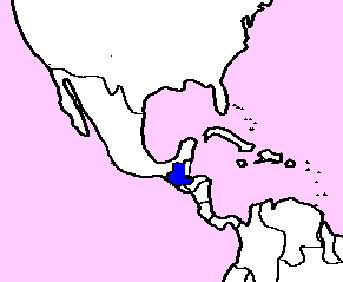
グァテマラは
●面積
約 10万平方キロ(日本の3倍程度)
●人口
約 1100万人
このうちの50−60%が先住民族
●公用語はスペイン語 そのほかに24の先住民族言語が存在 |
| 中米グァテマラはメキシコの南に位置する日本の3分の1ほどの小さな国です。しかしその小さな国土に豊かな多様性を秘めています。人口の6割を占めるマヤ民族を中心とする先住民族は、24の言語を有しています。あちこちの街で開かれる市場の賑わい。そこを訪れる女性たちの鮮やかな民族衣装。そして市場で売られる様々な種類の野菜や果物もそのような豊かさを現していると言えるでしょう |
★グァテマラの先住民族
グァテマラには大きく三つの民族グループがあります。一つにはこの地の征服者であったスペイン人の子孫など植民地期から現代に至るまでに移住してきたヨーロッパ系の白人などからなる非先住民のグループです。もう一つはガリフナ、シンカ、マヤの三つのグループからなる先住民族。この中でもマヤ民族の人口が圧倒的に大きく、マヤには22民族(言語集団)が含まれています。その中で人口が多いのはキチェ、カクチケル、ケクチ、マムなどです。またこうした二つのグループの混血化によって生まれた集団、あるいは先住民族としてのアイデンティティーを捨てた(捨てざる得なかった)人々もいます。 |
|
★社会から排除されているマヤの人々
先住民族マヤの人々は、グァテマラ社会の中でどのような地位に置かれているのでしょうか?
|
| 公用語がスペイン語だけ? |
グァテマラの公用語はスペイン語です。しかしグァテマラには20以上の言語があります。村に行けば、マヤの人々は日常的には自分たちの言語で会話をしていますし、特に女性たちはマヤの言語しか話さないことがまれではありません。
2003年に制定された言語法で、やっと先住民族言語を尊重し、促進することが定められ、基本的な社会サービスにも自分たちの言語でアクセスできるように定められました。
しかし現実にマヤの言語で提供されることはまだ多くありません。こうした中で地方と中央をつなぐコナビグアのような組織を通じての情報はとても重要です。 |
| 学校には行けるの? |
グァテマラの公的教育は遅れていて、平均就学年数は2.3年に過ぎません。これが先住民族の多い地域では1.3年になってしまいます。
また学校に行っても、多くの場合は一年生からスペイン語での授業でついていけずに落第することもままあります。いま、多言語教育も進みつつありますが、教員の養成、教材の整備など困難は多々あります。
ちなみに、女性たちの非識字率は地域によっては60%以上で、これは国平均の約31%(1998)という数字を大きく上回ります。これは、もともとマヤの人々の言語が文字言語ではないこともありますが、女性たちが学校へ行って、スペイン語を学ぶ機会が奪われているからでもあります。
|
| 政治は誰がやっているの? |
選挙に参加し、自分たちの代表を選ぶ、こうした権利は法的には認められていても、実際に行使することはとても難しいのが現状です。
まず、選挙に参加するためには大きな障害があります。農村部の多くの人たち、特に女性たちが住民登録をしていないため、それに基づく選挙人登録をすることができません。それに加えて投票所まで行くのにも一日がかりという村が数多くあります。
また近年先住民族から国会議員に立候補する人たちも増えてきましたが、現在でも国会議員の12.4%を占めるにとどまっています。(2000年)内戦時に多くのリーダーが殺されたことに加え、教育を受ける機会が限られていることも政治参加の障害となっています。
しかし地方自治体などでは、地域住民による市民政党の動きも活発化しつつあります。 |
| 法律は誰のもの? |
マヤの伝統的な慣習やしきたりは、現行法には活かされていません。「法律」はよそから押しつけられてきたものです。かってはその「法律」に基づいて、マヤの人々は強制労働などにかり出されたのです。
いまでも相変わらず、法律はマヤの法概念と結びついたものではありませんし、現実的にも法的な制度にアクセスすることがほとんどできません。そこにもスペイン語の壁があります。
いま、地域の人々の仲介による話し合いによる紛争解決など、新しく多元性のある法制度が目指されつつあります。
|
★グァテマラの内戦
グァテマラでは1962年から96年まで、36年間にわたってグァテマラ政府とゲリラ組織との内戦が続きました。1954年の米軍の介入によるクーデターの後、グァテマラにおける社会的な改革の芽はつぶされます。その後軍部の若手将校などを中心に、蜂起が起こります。ここにゲリラ勢力が生まれることとなりました。60年代中にゲリラ勢力は一度壊滅状態となりましたが、70年代に活動拠点を先住民族の多く居住する北部、西北部の高地に移し、住民の組織化などを進め、再建を進めました。
これに対し、軍部は弾圧を強め、選択的な誘拐、暗殺といった段階から、ゲリラのシンパと見なされた先住民族への虐殺へと転化していったのです。この過程で何百という村が焼き払われ、20万人の死者・行方不明者が生み出されました。こうした被害者のうち90%は非戦闘員であり、83%がマヤ民族であると言われています。この内戦は、86年の民政移管の後に進んだ和平交渉を経て、96年12月に終結しました。和平協定の中には、「先住民族の権利とアイデンティティー」や「社会経済・土地問題」などについて取り組むべき課題が示されていますが、和平後7年を経ましたが、まだ問題は山積しています。 |
|
| 2:コナビグアってなに? 戻る |
コナビグア(連れあいを奪われた女性たちの会)はまだ弾圧の内戦の弾圧の厳しいさなか、1988年に設立されました。内戦の中で、夫や子どもたちを軍に誘拐されたり、殺害された女性たちが、平和な社会を求めて活動を開始したのです。脅迫にも負けず、女性たちは「自警団」と呼ばれる、軍によって作られた人権抑圧組織の解体を求め、また徴兵制の廃止を求めて運動をしてきました。
1996年の和平合意以降、コナビグアは人権侵害の告発にとどまらず、先住民族を代表する組織としてまた先住民族女性を代表する組織として、グァテマラをより平等な社会にするために、様々な活動を展開してきました。
そうした活動が実って、軍役に代わる「社会サービス法」も制定されましたし、内戦被害者に対する補償問題も動き始めています。
しかしグァテマラ社会の中で、先住民族女性が受ける差別や貧困の問題はまだまだ大きく、コナビグアのさらなる活動が望まれています。 |
  |